
|
(1)
イ、今日の簿記会計の任務は、「期間損益」をいかに正確に計算し、事業年度末における財政状態をいかに客観的に把握するのか、という点にあるといってよいであろう。 ロ、「期間損益」をいかに正確に計算するのかとは、つまり、この1年間の営業努力を明らかにして、結果、いくらの利益を上げたのかを外部に報告することである。営業努力を明らかにするとは、この1年間(事業年度)に発生した収益と、これに要した費用を正しく把握することである。(こうした収益と費用の相関関係を「費用収益対応の原則」という) さて、期中における費用・収益の記帳は、主に現金や小切手などの収支による取引か、または商品などの現物の受払いによる取引に基づいて行われている。すなわち、費用・収益の発生にしたがって記帳されているわけではないのである。そこで、適切な経営成績を表わすために、期末において、期中の記帳金額を費用・収益の発生金額に修正する必要が生じる。 これを『損益整理』という。 ハ、さらに、財政状態をいかに客観的に把握するのかということは、期末における資産および負債の実際有高を確認して、帳簿価額との間に食違いがあるのかないのかを検証することである。 期中において行われにくい棚卸や時価調査をして、これらの事実に基づいて財産評価の修正を加えて、財政状態を明らかにするのである。 ニ、これらのことを『期末決算整理』といっている。
(2)
|
| 第1章 売上原価の算出について |
| 第1節 意義 |
期末に実地棚卸を行ない、売れ残り商品の実際有高を調べ、当期の売上原価を算出する。算出の公式は、以下のとおりであった。
| 第2節 公式 |

| 第3節 決算整理仕訳 |
(例)期首商品30円、当期商品仕入高400円、期末商品有高25円。
(仕訳)
| (売上原価) | 30 | (繰越商品) | 30 |
| (売上原価) | 400 | (仕 入) | 400 |
| (繰越商品) | 25 | (売上原価) | 25 |

| (仕 入) | 30 | (繰越商品) | 30 |
| (繰越商品) | 25 | (仕 入) | 25 |

ハ、実務法(資産としての商品a/c と費用としての繰越商品a/c で売上原価を算出する方法)
| (繰越商品) | 30 | (商 品) | 30 |
| (商 品) | 25 | (繰越商品) | 25 |
| (損 益) | 30 | (繰越商品) | 30 |
| (損 益) | 400 | (仕 入) | 400 |
| (繰越商品) | 25 | (損 益) | 25 |

| 第2章 棚卸資産・有価証券の評価替えについて |
| 第1節 意義 |
棚卸資産・有価証券にいくらの金額を付すのか(評価)についての考え方は以下のとおりであった。
イ、原則は取得価額(原価主義)で評価し、
ロ、ただし、低価基準が採用することができ、
ハ、なお、強制低価法が適用される。
| 第2節 決算整理仕訳 |
(商品評価損)×××(繰越商品)×××*
*には、(帳簿単価−時価単価)×実際数量=×××として算出された金額が記入される。
ロ、有価証券の場合
(有価証券評価損)×××(有価証券)×××*
*には、(帳簿単価−時価単価)×(株式数または社債口数)=×××として算出された金額が記入される。
| 第3章 貸倒引当金の設定について |
| 第1節 意義 |
期末における受取手形・売掛金などの貸金について翌期以降の回収不能額すなわち貸倒れ予想額を合理的に見積り、費用に計上する手続きである。
例えば、翌期に貸倒れが現実のものとなったとして、「貸倒損失」の費用をいずれの期に負担させるのが、正しい期間損益の考え方に合致しているのかという問題である。
貸倒れの発生は、もともとが他人・他企業に金銭を貸付けたところにその原因がある。つまり、貸さなければ、貸倒れは発生しないのである。よって、貸倒れがいつ現実のものとなるかどうかを問わず、貸付けを行なった「当期」が貸倒損失の費用を負担すべきであろう。
| 第2節 決算整理仕訳 |
第1項 洗替法
(貸倒引当金 )×××(貸倒引当金戻入)×××*1
(貸倒引当金繰入)×××(貸倒引当金 )×××*2
*1には、前期貸倒引当金の期末残高の金額を記入する。
*2には、(期末受取手形+売掛金など)×貸倒発生率=貸倒見積額として算出された金額を記入する。
第2項 差額補充法
(貸倒引当金繰入)×××(貸倒引当金 )×××*
*には、(期末受取手形+売掛金など)×貸倒発生率−前期貸倒引当金の期末残高金額=当期貸倒見積額−前期貸倒引当金の期末残高金額=×××として算出された金額を記入する。
なお、×××の金額がマイナスになるときは、以下の仕訳となる。
(貸倒引当金 )×××(貸倒引当金戻入)×××
| (補)貸倒損失勘定・貸倒引当金繰入勘定の2つの性質をあわせもった勘定として「貸倒償却勘定(費用)」を用いることがある。 |
| 第4章 減価償却費の計上について |
| 第1節 意義 |
固定資産の多くは、利用や時の経過にしたがってその価値を減少させる。その減価部分を合理的に見積り、期末に費用に計上する手続きを減価償却という。
すなわち、資産の消費部分は、「費用」として把握される。逆にいえば、資産とは、未消費の費用ということができる。

| 第2節 決算整理仕訳 |
第1項 直接法
(減価償却費)×××(〇 〇 ex. 備品)×××
第2項 間接法
(減価償却費)×××(〇〇減価償却累計額)×××
減価償却費の金額は、定額法の場合

減価償却費の金額は、定率法の場合
|
| 第5章 費用・収益の見越・繰延について |
| 第1節 意義 |
継続した役務提供契約において、時間的経過にしたがい「当期に属する収益と費用」を算出し、修正・計上する手続きを「費用・収益の見越・繰延」という。
すなわち、現金収支に基づく費用・収益のうち、未経過部分を次期以降に繰延べ、発生した費用・収益のうち、未記入部分を当期の損益に見込み計上することである。
| 第2節 費用の繰延 |
(例)4月1日に向こう1年分の保険料として現金240円を支払った。なお、期末(12月31日)に費用の繰延べをした。

4. 1(支払保険料)240(現 金)240
12.31(前払保険料) 60(支払保険料) 60
|
*前払保険料勘定は、「前払費用」勘定を用いてもよく、「資産」の勘定科目である。債権の勘定である「前払金」とは区別しなければならない。
*1年分の保険料240÷12×3=60として算出される。 *翌期首において、再振替仕訳をしなければならない。 1. 1(支払保険料) 60(前払保険料) 60 |
| 第3節 収益の繰延 |
(例)5月1日に向こう1年分の家賃として現金360円を受け取った。なお、期末(12月31日)に収益の繰延べをした。

5. 1(現 金)360(受取家賃)360
12.31(受取家賃)120(前受家賃)120
|
*前受家賃勘定は、「前受収益」勘定を用いてもよく、「負債」の勘定科目である。債務の勘定である「前受金」とは区別しなければならない。
*1年分の家賃360÷12×4=120として算出される。 *翌期首において、再振替仕訳をしなければならない。 1. 1(前受家賃)120(受取家賃)120 |
| 第4節 費用の見越し |
(例)3月1日に、期間1年・利率7.2%という約束で、現金500円を借入れた。なお、期末(12月31日)に、費用の見越し計算をした。

3. 1(現 金)500(借 入 金)500
12.31(支払利息) 30(未払利息) 30
|
*未払利息勘定は、「未払費用」勘定を用いてもよく、「負債」の勘定科目である。債務の勘定である「未払金」とは区別しなければならない。
*1年分の利息36÷12×10=30として算出される。 *翌期首において、再振替仕訳をしなければならない。 1. 1(未払利息) 30(支払利息) 30 |
| 第5節 収益の見越し |
(例)6月1日に、期間1年・利率12%という約束で、現金400円を貸付けた。なお、期末(12月31日)に収益の見越し計算をした。

6. 1(貸付金 )400(現 金)400
12.31(未収利息) 28(受取利息) 28
|
*未収利息勘定は、「未収収益」勘定を用いてもよく、「資産」の勘定科目である。債権の勘定である「未収金」とは区別しなければならない。
*1年分の利息48÷12×7=28として算出される。 *翌期首において、再振替仕訳をしなければならない。 1. 1(受取利息) 28(前受利息) 30 |
| 第6章 消耗品の期末未使用分の処理について |
消耗品などの物品は、原則として、購入時に費用処理してあるが、期末に未使用分があれば資産に計上することがある。
(例)期中に200円分の消耗品を購入したが、期末に45円分が未使用であることが判明した。
| (解1) | 期中 | (消耗品費) | 200 | (現 金) | 200 | |
| 期末 | (消 耗 品) | 45 | (消耗品費) | 45 | ||
| (解2) | 期中 | (消 耗 品) | 200 | (現 金) | 200 | |
| 期末 | (消耗品費) | 155 | (消 耗 品) | 155 |
| *期中に消耗品費(費用)で処理した場合は、期末に資産(消耗品)に計上しなければならないが、逆に期中に消耗品(資産)で処理した場合は、期末に費用(消耗品費)を計上することとなる。 |
| 第7章 その他 |
期末決算整理事項には、その他、本支店会計における内部利益の除去、割賦販売における未実現利益の繰延べなどがある。
*その他の決算時処理
現金過不足勘定は、借方(左)残高であれば雑損勘定へ、貸方(右)残高であれば雑益勘定へ振替える。
仮払金勘定・仮受金勘定や未決算勘定は、内容を明示する適切な勘定科目に振替えて、貸借対照表には表示しない。
| 第8章 精算表 |
| 第1節 意義 |
決算手続きの妥当性を確認するために、決算(帳簿締切り)の前段階として、精算表が作成されます。
残高試算表から「期末決算整理記入」を通して、損益計算書・貸借対照表を誘導・作成する一覧表を「精算表」といいます。
精算表には、8桁(欄)精算表・10桁(欄)精算表などがありますが、一般的に、商業簿記では「8桁(欄)精算表」が用いられます。
| 第2節 精算表の作成 |
(例題)

|
次の期末整理事項によって、精算表を完成しなさい。ただし、会計期間は、1月1日から12月31日までの1年である。
期末整理事項 (1) 受取手形および売掛金の期末残高の合計額に対して2%の貸し倒れを見積もる。ただし、貸倒引当金期末残高に補充する方法によること。 (2) 貸付金利息が¥21,450未収である。 (3) 商品期末棚卸高は¥1,155,000である。なお、売上原価は「売上原価」の行で計算する方法によること。 (4) 消耗品期末棚卸高は¥204,500である。 (5) 備品に対して定額法により減価償却をおこなう。残存価額は取得原価の10%、耐用年数は6年である。 (6) 支払保険料¥396,000は、3月1日に契約した向こう1年分の火災保険料である。 (7) 支払家賃は1月から10月までの支払額であり、以後も月あたりの家賃に変更はない。 |
決算整理事項を「仕訳」してみると、以下のとおりです。

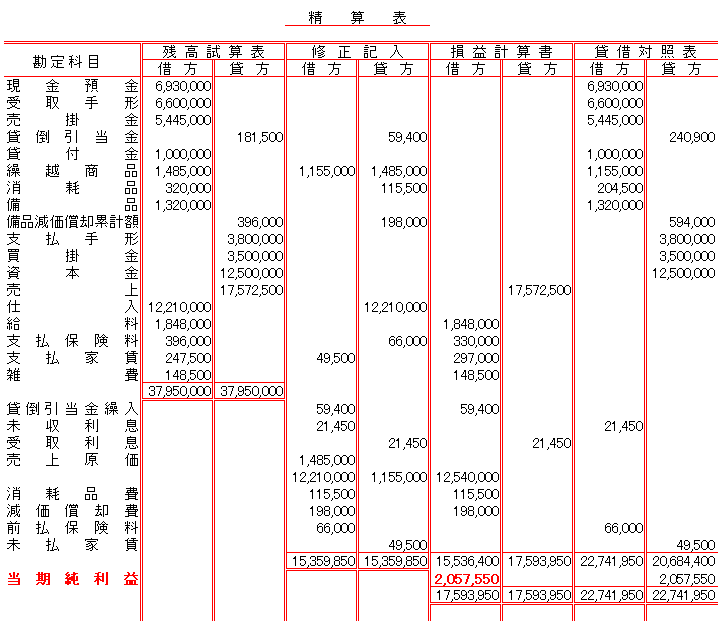 |